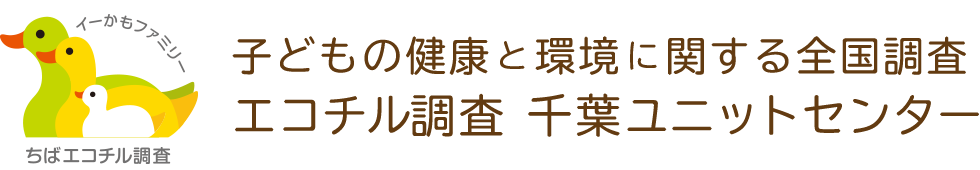キット先生の豊かな心をはぐくむ子育て<第22回>
「ちばエコチル調査つうしん Vol.27」(2025年9月発行)より一部改変して掲載)
多様な自己評価の大切さ
どう見られるか、どう評価されるか

私たちは、他者にどう思われているか、つまり、評価を気にします。気になる度合いは人それぞれであっても、全く気にしない人は、社会性に欠けると言われるかもしれません。
10年くらい前の話ですが、小学生の不安を調査したとき、日本の子どもの不安に特徴がありました。「人にどう思われるかが心配」という「社交不安」が高かったのです。
そういえば、友人の一人が、「小学校から中学校にかけて、手を挙げて発言することはなかった」と言っていたのを思い出しました。「変に思われたくなかった」そうです。他者の評価を気にする度合いが高いと生活にいろいろな影響が出るようです。
今は、SNSが他者の評価を一層「見える化」しています。東京都の児童とその養育者を対象とした調査(杉本 ・2012年)では、10歳女児のインターネットの使用と「やせ願望」の関連が明らかになったと報告されています。
その調査では、女児の多くが小学生のときからやせたいと思っていて、それにSNSが影響しているという結果が示されました。しかし、男児には関連は見られなかったそうです。
オンラインの影響

オンラインの影響はいろいろ報告されています。NHKの調査によると、小中高校生のダイエット情報を交換する「オープンチャット」グループが50件ほどあったそうです。過激なダイエット方法を紹介し合う、減量を競い合うなどのグループもあったそうです。やせたスタイルを基準とする自己評価に、SNS利用が深く関係するということがわかります。
オンライン使用について私の研究チームも小中学生を対象に調査しました。多くの児童生徒が、オンラインの良い点も理解し、時間の問題や交友関係に与える問題なども認識していました。オンライン使用の長所と短所を理解しているという結果は評価できました。
しかし、「やせ願望」など身体への自己評価に与える影響は認識しにくい傾向があるのではないでしょうか。子どもたちが気づきにくい問題には、当然、大人の理解と支援が必要になります。
ボディイメージ

ボディイメージとは、自分の身体の大きさや形に対する自分自身の理解のことです。イメージできるという能力は大切です。イメージできるから、特に意識して手を動かさなくても欲しいものに手を伸ばして取ることができます。
ただ、自分の身体に対するイメージは自己評価につながります。「大きな目、やせたスタイルの方がよい」と思い込み、自分のイメージがそうでなかった場合は自己評価を低くしてしまいます。
ボディイメージは、個人的な経験や文化的規範、社会的期待に影響を受けます。今の社会では、「かわいい」「きれい」「かっこいい」など、外見が高く評価されがちです。外見によって人を評価・判断・差別することを「ルッキズム」と呼びますが、このルッキズムが評価基準となる傾向の強い社会は、私たちに大きく影響しているように思います。
昔は、「勉強ができる」「速く走れる」「スポーツが得意だ」「お手伝いをする」「みんなと仲良くできる」など多様な評価基準があり、子どもたちも、外見とは別のさまざまな事柄で自己評価ができました。
現代は多様性が尊重される時代であるはずなのに、子どもたちは、外見という一つの判断基準がとても強い現実の中で暮らしています。
そして、今まではマスメディアによる影響を受け取る側でしたが、フェイスブックやユーチューブなどのSNSでは、受け取るだけでなく送る側にもなっています。その両面により、影響を受ける側と影響を与える側の区別がわかりにくくなっています。
あるユーチューバーの影響を受けた人が、今度は発信者となって、また別の多くの人に影響を広げていきます。この複雑な環境の中で女児たちの「やせ願望」が生まれ、強くなると、自己認識や健康の問題が起こってしまうのです。
ベネッセの研究では、子どものSNS使用に親が関わると、子どもの自己肯定感が向上するという結果報告がありました。でも、保護者の皆様には、子どもにどう関わるかを考える前に、次のことを考えてほしいと思います。
・ルッキズムやSNSをどう思いますか?
・それらの影響をどのくらい受けていますか?
大人もダイエットに関心があり、実行しています(健康上の理由もありますが)。SNSで見た何かを買う、どこかに行くなどの影響も大きいです(情報として収集する場合もありますが)。毎日の生活の中で、私たち大人の認識と生活もまた子どもに大きく影響しています。
SNS使用をサポートする

❶ SNSについて話す
たとえば、ユーチューブについて子どもと話します。ユーチューバーにはその投稿を多くの人が見るほどお金が入る仕組みになっていること、注目を集めるために人の気を引く情報をどんどん提供してくるため、次々に見てしまうようになっていることなど。知っているつもりのことでも、改めて言葉にして話し合ってみることで、批判的な見方を育てることができます。
SNS利用そのものを批判するのではありません。うまく利用する姿勢を育てていくために、批判的に考える力を育てる話し合いは必要です。多くの人に見てもらうためにユーチューバーはどうしているのか、それは本当に自分の役に立つ正確な情報なのか、どんなことを学べるかなど、話し合ってみましょう。
❷ 自己認知の力を育てる
「自己認知」という力を育てます。自分の感情や考えに気づく、自分の強みを知る、自信を持つなどの力です。社会性と感情の学習(SEL)では、スキルとして練習を通じて育てますが、保護者や先生方の声かけや話し合いで育てることもできます。自分の感情と考えに気づくのは、自己コントロールにつながります。また、どんな強みがあるかに気づく支援をします。自分の強みを知るのは、自信につながります。
子どもの気持ちや考えを聞き、耳を傾けます。自信を育てるために、何かを頼んだり、一緒にしたりしましょう。具体的な行動や言葉、頑張って取り組んでいることやその成果をほめましょう。そして、感謝しましょう。
外見による自己評価だけにならないよう、多様な自己評価ができる力、そして、他者評価に簡単に左右されない自分の軸をつくる力を育てましょう。