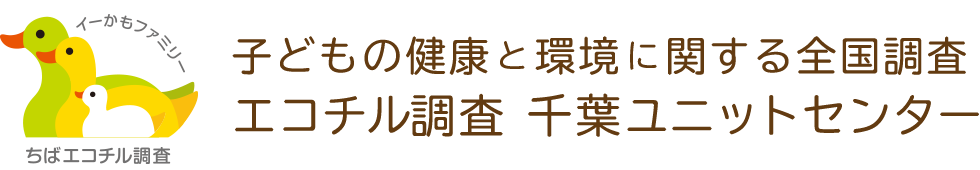キット先生の豊かな心をはぐくむ子育て<第21回>
「ちばエコチル調査つうしん Vol.26」(2025年3月発行)より一部改変して掲載)
子育てのイライラへの対応

子どもにイライラしてしまうと、そんな自分がイヤになったり、イライラさせる子どもの行動がストレスになったりします。「子育てにイライラはつきもの」という意見もありますが、イライラしない子育てはどうすれば実現するのでしょうか。そもそも実現できるのでしょうか。
以前、「いつも子どもが言うことをきかないのでイライラしてしまう」というお母さんの相談を受けました。そこで、一週間、「子どもの行動記録」をつけてもらうことにしました。言うことをきかない行動を見たらチェックを入れるというシンプルな記録です。
そして一週間後、記録して気づいたことを話してもらうと、「自分が思っていたより子どもが言うことを聞いていたことがわかった」ということでした。
このお母さんは、もしかしたら今までずっと子どもの行動や感情を勘違いしていたのかもしれませんが、もう一点、他の説明もできるのではないでしょうか。
このお母さんは、子どもに年中イライラさせられていたわけですが、行動記録に取り組んだ一週間は、かなり理性的に観察していた様子がうかがえます。
大げさに聞こえるかもしれませんが、科学的な方法でイライラ反応の妥当性を測ったことで、少し距離を置いて子どもと自分のやりとりを観察することができたのではないでしょうか。そうすることで、子どもと自分の感情への理解が進んだように思えます。
子育てのイライラは、親がその時々の子どもの行動をどう捉えたかに関係するのではないかと気づいた事例です。
親が、いつもエネルギーにあふれ、理性的に考えて行動し、子どもにやさしく接するのは、現実的にはむずかしいでしょう。子どもが毎日24時間よい子でいるのがむずかしいのと同じです。でも、前向きなやりとりの中で、互いに成長し合っていけると期待できます。
子育ての研究によると、親のイライラにつながる考えや感じ方には二つの特徴があるということです。
一つ目は、完璧主義です。でも、子どもは毎日の経験を通じて社会性や行動規範を少しずつ学んでいくもので、そのスピードはそれぞれです。親の方も、子育てを勉強してから親になるのではなく、親となってから子育てを学んでいきます。実践しながら学んでいくので完璧な成果を期待するのは無理があり、60~70%の期待値でも高いかもしれません。
二つ目は、「子どものせいで何らかの犠牲を強いられている」と感じるとイライラ感が募るというのです。確かに、子育て中は自由な時間が減り、自分を犠牲にしているように感じるかもしれません。しかし子育ては、創造的で生産的な体験ができる貴重な時間でもあります。
また、子育て中に自分の時間を持つ方法を考えるのは可能です。イライラ感情の元になっている考えや感じ方に気づけば、対応できる方法につながるのではないでしょうか。
子育てのイライラ感情に大きく関係するもう一つの考え方として、「子育ての責任は親にある」という意識があると思います。でも近年では、子育てを社会全体で支える方向に動いていて、各地域で様々な支援が行われています。
子育て支援の情報を知り、必要な支援を求める子育てができるとイライラ対応の方法につながるのではないでしょうか。
自分や相手の感情を理解することによって、社会の中で適切に行動できるための知識やスキルを学習することを「社会的情動(感情)の学習(SEL)」と呼びます。
❶ 自分を理解する力
❷ 自分をマネージメントする力
❸ 他者を理解する力
❹ 対人関係力
❺ 責任ある問題解決力
この5つを核とする社会的情動(感情)の学習(SEL)は、これからの社会に必要な子どもの力を育てる学習として広がっています。
自分の感情やニーズを理解し、自分を大切にすることは大人にも必要で、子育てにも発揮して欲しい大切な力です。
※「社会的情動(感情)の学習(SEL)については、ちばエコチル調査ホームページ内「キット先生の豊かな心をはぐくむ子育て・第10回」で詳しく説明しています。
子育てのイライラに対応するポイント
1.感情のラベリング(感情を名づける)とレベル測定で感情力アップ
今回は、子育てする自分の気持ちを受容するスキルから始めます。
イライラしている、悲しい、腹立たしいなど、自分の感情とそのレベルに気づきます。
一番低いレベル1から、一番高いレベル10まで感情測定しましょう。自分の感情に気づけば、対応する方法を見つけ実行することができるのです。
イライラしているけれど、何とか落ち着いて話ができるのなら大丈夫です。でも、イライラ感が強いまま子どもにかかわるのは、子どもも自分も傷ついてしまう可能性があります。
2.高レベルのイライラに対応し自己マネージメントアップ
イライラの度合いが大きく、長く続くと、対応が必要なレベルです。そんなときにどうするかを考えておきます。
実践例として、深呼吸する、お水を飲む、静かな場所にしばらくいる、などがあります。それで気持ちが変わるのかと疑問に思うかもしれませんが、脳の働きからみると、感情理解(感情のラベリングとレベルの測定)の段階でかなり落ち着いているのです。
イライラのレベルが下がったら、子どもにどう声かけをするかを考えます。イライラする場面が決まっていれば、前もって言葉を考えておくとよいでしょう。
「はっきり穏やかな指示」は、子どもの年齢にかかわらず役に立ちます。そして、小さなことでも子どものよい行動を見たら、ほめることも大切です。自己マネージメントの力を使います。
3.サポーターに頼るのは社会的な問題解決力
「自分の時間が欲しい」と思うのは自然なことです。「自分を大事にすることで、他者も大事にできる」というのはよく聞く言葉です。家族、知人で、お世話をお願いできる人がいれば、お願いしましょう。身近なサポーターの存在に気づくと気持ちが楽になります。
地域の支援も利用しましょう。子育てを他人や社会に頼ることに抵抗がある人もいるでしょう。でも、各地域に子育て支援サービスがあるのは、社会的に認められている問題解決方法だからです。
子どもにとってもメリットがあります。子ども自身が多くの人と出会い、自分を理解し応援してくれるサポーターを得る機会になるのです。つまり、親にも子どもにも役立ち、対人関係を作る学びがあります。
いざというときのために、こういう場合は誰に、どこにお願いすると書き出したサポーターリストを作っておきましょう。子どもの意見を聞いて作るサポーターリストも素敵ですね。